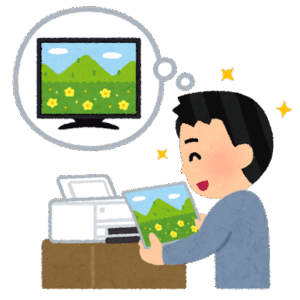生成AIと税理士業務
最近「生成AI」や「ChatGPT」といった言葉を耳にする機会が増え、PCに詳しくない私でも無視できない存在になってきました。税理士業界にもその波が押し寄せており、いくつか研修を受けたり、自分でもChatGPTを少しだけ試してみたりしています。実際に触れて、税理士業務との関わりについて感じた事を、簡単にまとめました。
1. 研修資料は“90点の出来”
AIが作成した研修用のパワーポイントは、正確で参考文献も明示されており、一見優秀です。しかし、どれも無難な内容で個性や熱意が感じられず、「感動」までは届かない印象です。講師いわく、作成時間は10分程度との事。便利ではありますが、やや物足りなさを感じました。
2. 個別対応はまだ難しい
例えば「相続税を最も安く抑える方法」といった一般的な問いにはそれなりの回答が返ってきますが、「この相続人には多く、あの相続人には少なく…」といった感情や事情を踏まえた相談には不向きです。個別具体性には、まだ人間の思考が必要です。
3. 情報が少ないと誤回答も
ローカルな話題、たとえば子供が通う小学校の学区について聞いても、うまく答えられない事があります。信頼性は情報量に左右されるようです。
4. 比較は得意分野
一方、複数の選択肢を比較する用途では非常に優秀です。不動産会社の特徴を一覧化するなど、これまで自力で調べていた作業が一瞬で完了します。
AIがどれほど進化しても、税理士が求められるのは「個別性への対応力」です。今後は顧問先がAIで調べた上で相談してくる時代になるかもしれません。一般的な情報はAIを活用しつつ、専門家としての価値をどこに出すかが問われる時代が来ていると感じています。